会社を作るまでの中心人物を発起人といいます。発起人は、会社名、目的、所在地、出資金、役員など、会社の骨組みを決定しなければなりません。これらは会社設立後に変更があった場合、その都度登記事項を変更しなければなりませんから、慎重に決定する必要があります。登記事項変更するのには費用がかかります。裏を返せば、手間とお金を惜しまなければ後から変更も可能なので、最初のうちに目的や事業内容などは欲張って書かなくても大丈夫といえば大丈夫です。
会社に引継ぐ財産
個人事業主からの法人成りの場合、ほとんどの場合は何かしら引継ぐ財産があるでしょう。引継ぐ方法は2種類あります。現物出資というかたちで資産を移行する方法と、個人と会社間で売買して引継ぐ方法があります。

現物出資は、会社設立後の賃借対照表に記載できるものであれば何でもその対象とすることができます。ただし引継ぐ金額は原則時価でなければなりません。あまりにも時価からかけ離れた金額にすると、出資者に対して対価以上の株式を贈与したと認定されかねませんから注意が必要です。会社設立後に無償で資産を譲り渡すという方法もありますが、無償で渡してしまうとその財産の時価相当額を会社に贈与したことになります。そうなると思わぬ課税の可能性もありますからおすすめできません。
次に、会社に売却する方法ですが、この場合も時価で売ることに注意が必要です。売却する場合、消費税の対象になることにも注意が必要です。個人側が消費税の課税事業者である場合には、最後の確定申告で消費税の納付が増えることになります。
会社に引継げない財産
中には引継げない財産もあります。個人事業主時代に持ち家を自宅兼事務所として使用していた場合、家を会社へ引継ぎたくなります。しかし、住宅ローンの返済が途中の場合、抵当権が付いています。抵当権がある場合は、会社の資産にすることは不可能となります。この場合は、自宅を会社へ貸し出すかたちにするといいでしょう。その際に注意が必要なのは、個人側に家賃所得が発生してしまうので、個人事業主を廃業したとしても、確定申告は毎年行う必要が出てきます。
物件がリースだった場合は、そもそも会社の資産にはできませんから、リース会社との契約を設立した会社との契約に変更すれば完了です。
小規模企業共済に加入していた場合は
この場合は、一定の要件を満たせば引き続き維持することができます。一定の要件とは、
- 個人事業の廃業で、共済の解約理由はできるが、その共済金を請求しないこと
- 個人事業の廃業後1年以内に法人成りがあった旨を申し出ること
- 法人成りした後も小規模企業共済に加入できる資格を保有していること
これらを満たしているケースです。この継続のことを、掛金納付月数の通産といいます。
また、経営セーフティー共済の契約も、一定の要件を満たせば引き続き維持できます。
- 法人成りがあってから3ヶ月以内に申し出ること
- 法人成り後も中小企業者であること
- 法人成り後も引き続き加入条件を満たしていること
- 個人事業主時代に貸し付けられた賃金などの弁済を行うこと
この継続のことを、共済契約の承継といいます。
会社の代表印の作成
社名が決まれば、会社としてのはんこを用意する必要があります。会社名と役職名を印字する必要があるので、「株式会社△△△代表取締役印」と彫られているものを作成してください。このはんこを、代表印や実印といいます。
このはんこは銀行印としても使用することができます。そしてこのはんこは、会社の登記申請と共に法務局で印鑑登録します。ちなみにはんこのサイズは、最小サイズは1辺が1cmを超える正方形で、最大サイズは1辺が3cm以下の正方形となっています。
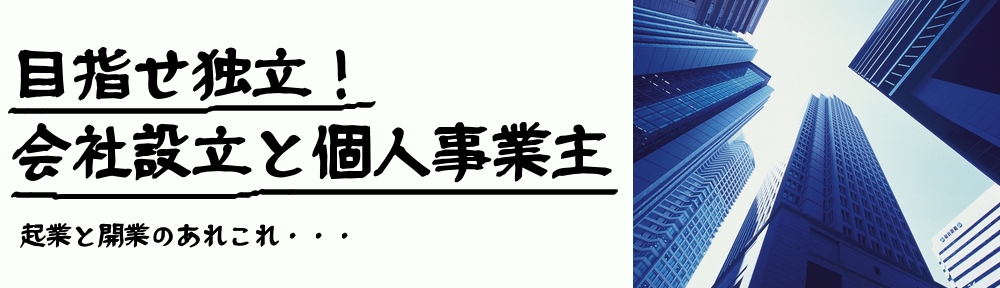
 個人事業主から法人成りの会計処理
個人事業主から法人成りの会計処理 経営セーフティー共済と小規模企業共済
経営セーフティー共済と小規模企業共済 会社の決算手続き
会社の決算手続き 個人事業主から会社設立までの手順
個人事業主から会社設立までの手順 経費となるもの、ならないもの
経費となるもの、ならないもの 会社は資金調達が楽
会社は資金調達が楽 会社を複数作るメリット
会社を複数作るメリット 新会社法で会社が作りやすくなった
新会社法で会社が作りやすくなった